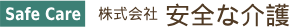ルール違反によって重大事故が発生すると職員個人が刑事責任を問われることがある
【検討事例】リフトでバランスを崩して溺水、肺水腫で死亡
Mさん(90歳女性)は要介護度4の特養入所者で、入浴介助は固定式のリフト浴で行っています。ある日、介護職員(介護福祉士)がMさんを入浴させようとすると、いつものように安全ベルトの装着を嫌がります。安全ベルトの材質が硬いため、きちんと装着すると肌が痛いのです。仕方なく安全ベルトを装着せずに、そのままリフトを浴槽に下ろしましたが、お湯に浸かる時に突然バランスを崩して、顔がお湯に浸かってしまいました。介護職員は慌ててリフトを上げましたが、Mさんがひどくむせ込むので、看護師を呼んでバイタルチェックの上、居室で安静にして様子を見ることにしました。
ところが、その日の晩11時頃、Mさんがひどく咳き込み、唾液に血液が混じっていたため救急搬送しました。病院では、カテーテル挿入時に血尿が見られ、吐血もあったためICUで抗生剤の点滴投与を受けました。医師が「雑菌の多い風呂のお湯が肺に入り肺水腫を起こしている」と駆けつけて来た息子さんに説明したため、激怒して相談員に詰め寄る息子さんに対して、「リフト浴の介助ミスでお湯に顔が浸かってしまった」と相談員が何度も謝罪しました。
Mさんが翌日死亡したため、警察が業務上過失致死の疑いで介護職員に事情を聴取しましたが、事件性なしとして捜査はありませんでした。しかし、息子さんは職員に事故状況を聞いて回り、安全ベルトの不装着が事故原因であったことを聞き出し、加害者である職員と施設長を警察に刑事告訴しました。施設長は損害賠償金の上乗せを提示しましたが、「施設は事故を隠ぺいしようとした、許せない」と言って交渉には応じてくれません。
■事故の隠ぺいと受け取られた
リフト浴でバランスを崩して溺水し浴槽のお湯を飲んだことは、明らかな事故でありヒヤリハットではありません。事故が発生した時家族連絡を入れること、経過観察する場合に家族の了解を得ることは事故対応の原則です。
ところが、勝手な判断でルールを曲げる職員がいます。「誤薬したのに家族連絡もせず経過観察をする」「誤えんしたがすぐに回復したので家族連絡せず受診もしない」などの事例が見受けられます。その後も利用者に何らの損害も発生しなければ、事故事実を家族に知らせない施設さえあるのです。
しかし、意図に反して経過観察中に重篤な容態に陥った時、家族は施設の事故対応を、どのように受け止めるでしょうか?「事故を隠ぺいする意図で受診をしなかったために、適切な処置が遅れ重篤な容態になった」と考え、事故よりも組織ぐるみの隠ぺい工作が重大な不正であると考えます。
事故発生時に家族連絡しないことについて、「家族を煩わせたくないから」と言い訳をする施設がありますが、もってのほかです。事故後の迅速な家族連絡を励行することは、何も隠すことなく家族に知らせている、という姿勢を表すことにもなるのです。施設内で起こることを全て家族が知ることはできませんから、重大事故になればちょっとした疑いでも重大な疑惑になることを肝に銘じなければなりません。
■事件性がないのに刑事告訴されるのか?
同じ過失でも、ちょっとした不注意から起きる事故と、誰の目にも明らかに危険と考えられる行為によって起こる事故があります。前者は過失が軽いと判断され、後者は過失が重いとみなされます。職員の過失が重い事故で、死亡などの重大な事故に至れば、職員個人が業務上過失致死傷罪という刑法の罪に問われることがあります(※)。過失が重い(重過失)と判断されるのは、著しく注意を欠いた場合やルールに違反して故意に危険な行為を行った場合などですが、職員個人の注意義務が関係するケースもあります。
事故を起こした職員個人が特別高い注意義務を課されている場合などは、刑事責任が問われやすくなるのです。具体的には、看護師や介護福祉士などの国家資格を持つ者や、職場の安全管理責任を負っているような管理者の職位にある者などが該当します。
実際に、看護師はその国家資格によって高い注意義務を要求されているので、極めて初歩的なミスで重大事故を起こすと、業務上過失致死傷罪に問われるケースが珍しくありません。同様に国家士資格者である介護福祉士も高い注意義務を課されているのです。
本事例ではおそらく事故の直接の結果として死亡しなかった(溺死ではなかった)ので、警察は事件性なしと判断したのでしょう。しかし、故意に安全ベルトの装着を怠った介護職員の過失責任は重く、また、このように明らかに危険な業務を放置した管理者の責任も同様に重いと判断され、被害者から刑事告訴されてしまったのです。被害者が刑事告訴に踏み切ったのは、職員と管理者の責任の他に「隠ぺいしようとした」という組織の責任を追及したかったのかもしれません。
実際に施設の業務運営や設備環境などを、詳細にチェックしてみると常識では考えられないような危険が何の対応もなされず放置されていることが良くあります。特に入所施設は家族の目に触れない部分が多く、チェックが入りにくいので、外部の目で安全管理体制の点検をしない限り改善するのは難しいと思われます。
※刑法第211条:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
■介護事故で職員が刑事告訴されたら
職員が故意に安全ベルトを装着しなかったために、利用者が浴槽で溺れたのですから、過失が重いことは間違いありません。職員は介護福祉士という国家資格を持つ注意義務も高い者ですから、その責任が重いことは明白です。その上家族は「事故を隠ぺいする意図で経過観察したことが死亡という重大な結果を招いた」と考えていますから、被害者感情はピークに達して、「損害賠償だけでは許せない」と感じています。当然加害者である職員や施設を罰してやろう、という感情が湧いてきます。
事故の発生状況から警察が事件性なしと判断すれば、加害者が刑事責任を問われることがありませんが、被害者は加害者に対する刑事罰を求めて、警察に対して刑事告訴を行うことができます。警察が告訴状を受理すれば、事件として捜査され加害者が刑事罰を受ける可能性があります。
本事例では、警察が業務上過失致死の疑いで介入した段階で、被害者の遺族への対応を手厚く行うべきだったのです。具体的には、理事長などの地位の高い法人の経営者が直接何度も謝罪に足を運ぶこと、安全管理の手落ちを認めて公表し再発防止策を具体的に提示することなどです。そのような対応で実際には被害者は刑事告訴に踏み切ることを思いとどまるケースが多いのです。刑事告訴後であっても被害者への対応によっては告訴を取り下げるケースもありますから、まだ、手遅れではありません。経営者らは被害者遺族に対して誠心誠意の対応をすべきなのです。
交通事故や労災事故などで過失の重い重大事故が発生すると、警察が事件性なしと判断しても、被害者感情を癒すことを重要視して、経営者自ら何度も弔問に訪れるのは被害者の刑事告訴を怖れるからです。介護事業を運営する法人の多くが経営者に当事者意識が乏しく、法人の致命傷につながりかねない危機への対応体制がありません。
■装着しにくい安全ベルトは製品欠陥
最後に「肌が触れると傷ができるほど硬い材質で全ての利用者が装着を嫌がる」という安全ベルトも、大きな問題です。安全ベルトはリフト浴という介護機器が持つリスクを防止するために必要不可欠の安全装置です。入浴用の機器ですから素肌に直接触れることが前提の安全装置なのに、硬い素材で肌が傷ついてしまい装着しにくいのです。このことは、安全装置が機能しないことを意味していますから、製造物責任法の製品欠陥に該当します。ですから、本事例の損害賠償責任も最終的にはメーカーが負担することになるかもしれません。
しかし、施設はこの事故はリフト浴の安全ベルトが原因として、被害者にメーカーに賠償請求するよう求めることはできません。施設は安全な機器を用いて安全なサービス提供をすべき契約上の債務を負っているのですから、「安全な性能の危機に買い替える」「機器の安全性に問題があればメーカーに改善させる」などの対応をしなければなりません。このような介護機器には安全性に関わる製品欠陥が大変多く見受けられ、施設が漫然と放置しているので、事故もたくさん起きています。介護機器メーカーも、「プロなんだから危険な製品も工夫して使用すべき」と改善しません。
消費者庁などから、再三にわたって注意喚起をされているにもかかわらず、施設における介護機器の安全性に対する認識は全く向上せず、多くの機器が危険なまま使用されています。本事例の安全ベルトもメーカーに要求して改善させておけば、刑事告訴という職員個人が罰則を受ける事態には至らなかったはずです。